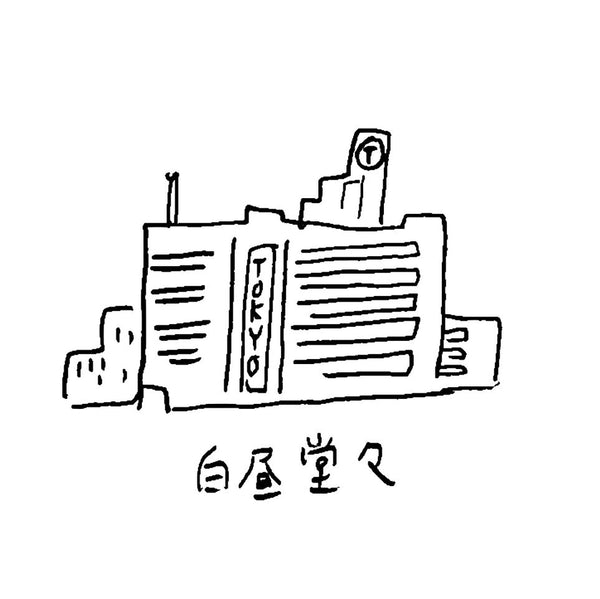ヒマラヤの奥地を長く歩いていると、カラダが主張をはじめる。
タンパク質をよこせ、と。
じゃがいもはある。トウモロコシもある。運がよければダル(豆)もある。
しかし、肉がない。とくに標高が上がり、集落もまばらになってくると、動物の気配すら薄くなる。肉という存在が、急に遠いものになる。
ここから一週間は野営か、という行程も珍しくない。担いできた米をたんまりと炊き、じゃがいも炒めとスープでとにかく腹を満たす。理屈ではそれで足りるはずなのだが、カラダのどこかが納得していない。何かが欠けている。
そんなとき、肉が現れる。
なぜ肉が?
答えは単純で、ネパール人の仲間がどこからか仕入れてくるのだ。野営地にたどり着くと、まるで当然のようにそれは彼の背負いカゴから姿を現す。
スクティである。
スクティは、干し肉のことだ。ネパールの山間部では、昔からの保存食であり、貴重な栄養源。冷蔵庫などあるはずもない土地で、肉を季節を越えて食べるための知恵である。水牛の肉を細長く切り、天日で干すか、あるいは煙で燻す。つくり方は驚くほど素朴で、塩と香辛料で下味をつけて干す。それだけと言っていい。
天日干しは、肉そのものの旨みがぎゅっと凝縮された味がする。余計な飾りはなく、噛めば噛むほど、塩気と肉の滋味がじんわり滲み出る。燻したものは、そこにスモーキーな香りが重なる。ヒマラヤの気候に通じるような、乾いた煙の匂いだ。
どちらもいい。甲乙つけがたい。ただ、どちらか選べと言われれば、私は天日干しに軍配を上げる。クセがなく、まっすぐに肉の力を感じられるからだ。
そういえば、水牛の肉をトタン屋根の上で天日干ししている光景を、これまでに何度か目にしたことがある。ネパールでは飼料を屋根の上で干していることが多いから、最初は何かのエサだろうと勝手に思い込んでいた。
細長い茶色いものが無造作に並べられ、強い日差しを浴びている。特別な食材には見えなかったが、あれこそがスクティだったのだ。しかも、仲間はそこからさりげなく仕入れていた。ネパールの屋根は、人のためだけでなく肉のためにも働いている。

標高4,000メートル前後、集落もない場所でテントを張り、スクティを炒める。冷えた空気のなかで、温かいブラックティーもしくはタトロキシー(温めた焼酎)と一緒に、スクティをかじる。
最初は、なかなか歯が立たない。けれど、しばらく格闘していると、次第に繊維がほぐれ、旨みが口のなかに広がっていく。塩気と辛みが、乾いたカラダにすっと染み込む。
うまい。
僻地で食べる肉というのは、その希少性もあってか、すこぶるうまい。カラダがはっきりと喜んでいるのがわかる。
本当に元気になる。力がみなぎる感じがする。
感じがする、と書いたのは、それがあくまでイメージだからだ。おそらく即効性だけでいえば、エナジージェルやサプリのほうが合理的なのだろう。
それでも、スクティにはそれらを凌駕する何かがある。覚醒作用とでも言おうか。
硬い肉を噛みしめるたびに、生きているという実感がじわじわと広がる。それは栄養が吸収されるというよりも、肉そのものが自分の血となり、筋肉の一部になっていくような感覚だ。
大げさかもしれない。だが、標高4,000メートルの夜にそれをかじると、本当にそう思えてくるのだ。
そんな経験をしてしまったからだろうか。いま私は、カトマンズというネパールの都会に住みながらも、週に一度はスクティを食べている。場所は近所の飲み屋だ。
もちろん、ヒマラヤ奥地で味わったあの高揚感、恍惚感はない。空気は薄くないし、疲れ切ってもいないし、自然の厳しさもない。それでも、硬い肉を噛むたびに、どこかカラダの奥が納得する。
頻度を考えれば、私の血となり肉となっているのは、間違いなくこちらのスクティのほうだろう。
スクティを食べると、あの日のヒマラヤに帰りたくなる。Himalaya is calling.
なんて言えたら、さぞ格好がいいのだろうが、まったくもってそんなことはない。スクティを食べたからといって、ヒマラヤの光景が蘇るわけでもない。
目の前のスクティがうまい。ただそれだけだ。